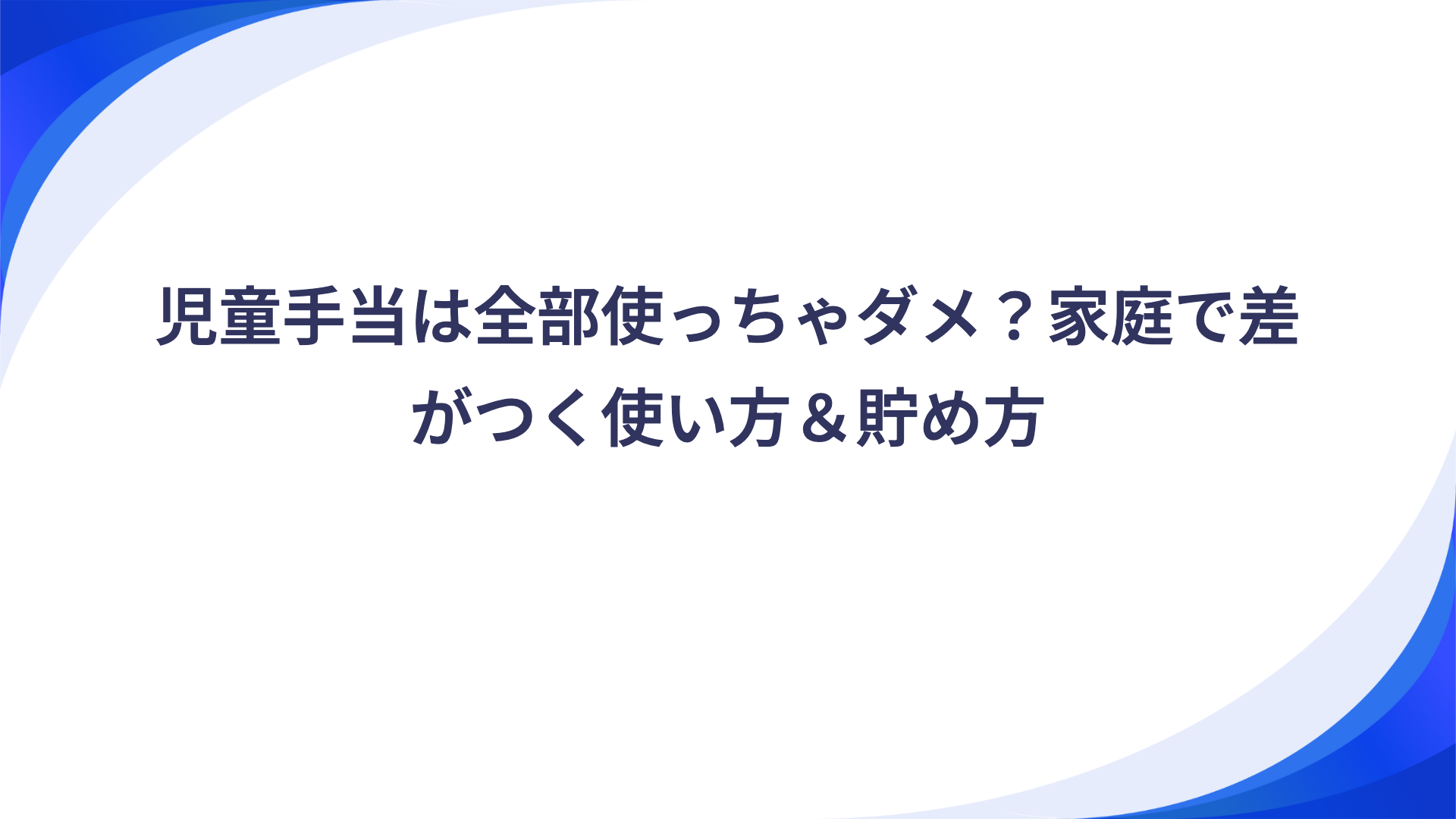パパでもできる!赤ちゃんが生まれる前にやっておきたい家計見直し術
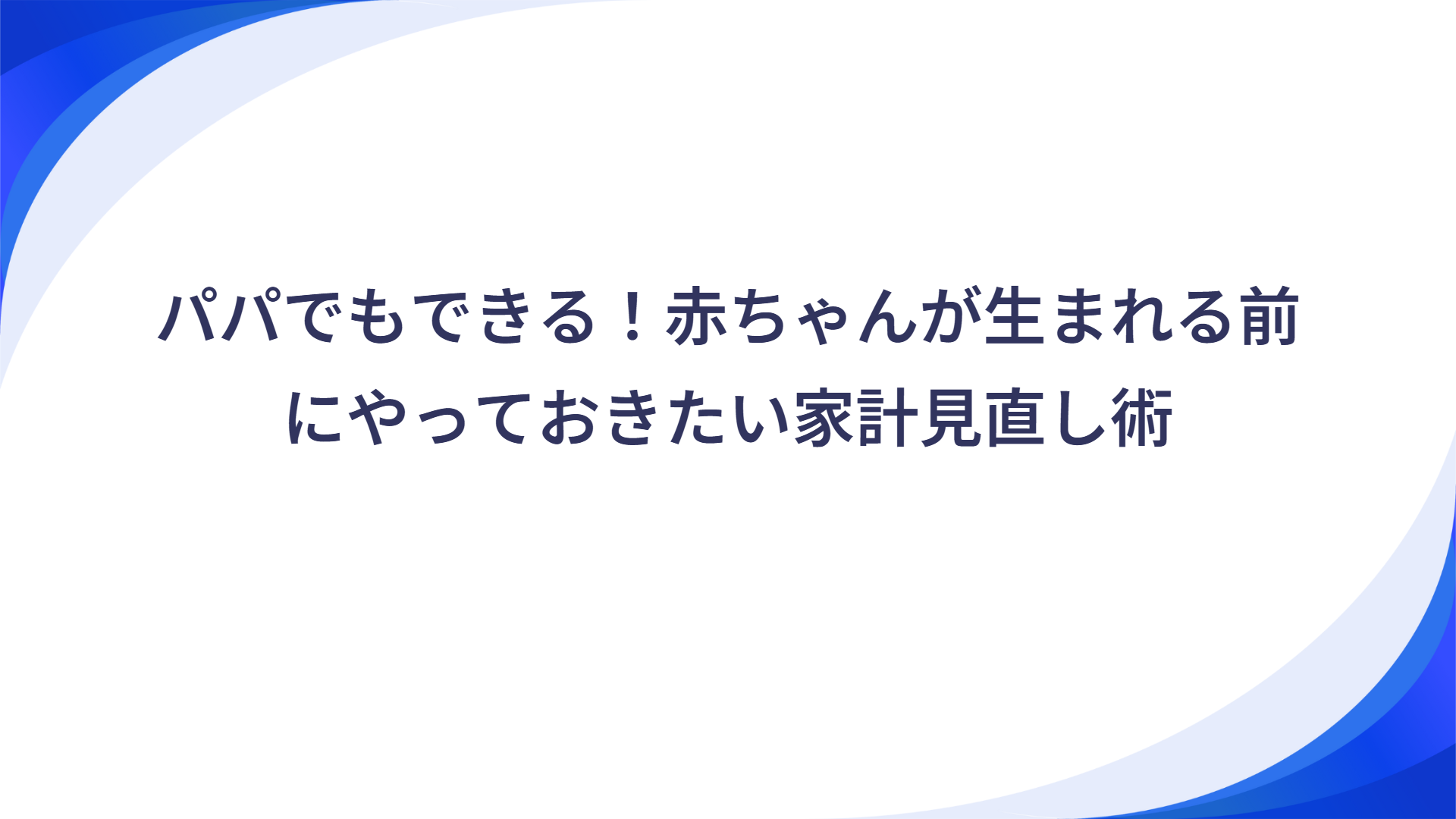
「赤ちゃんができた!」という嬉しいニュース。
でもその直後、頭にふとよぎるのは――
「これからの生活、ちゃんとやっていけるのかな…?」というお金の不安ではないでしょうか。
特にこれまで家計をあまり意識してこなかったパパにとって「何から始めればいいの?」と戸惑ってしまうのも当然です。
でも、大丈夫。
妊娠がわかった“今”こそが、家計の見直しを始めるベストタイミングなんです!
このブログでは、家計管理初心者のパパでも無理なく取り組める「家計の見直し術」をわかりやすく紹介します。
家族が増える“前”に、未来の安心を少しずつ形にしていきましょう。
- 赤ちゃんが生まれる前にやるべき家計の準備
- 家計見直しでチェックすべき3つの視点
- パパでも簡単にできる節約&お金の整え方
なぜ赤ちゃんが生まれる“前”に家計を見直すべきなのか?
赤ちゃんが生まれてからは、
「おむつ」「ミルク」「医療費」「洋服」「ベビーカー」
など、想像以上に出費が増えます。
生まれた“後”に焦って家計を見直すよりも、妊娠中の今のほうが心にゆとりをもって準備できます。
また、出産直後はママの体調や赤ちゃんのお世話に追われ、ゆっくりお金のことを考える時間がありません。
パパが今から動くことで、家族の安心感がぐんと高まります。
まずはここから!家計見直しの3ステップ
家計の見直しは、
「収入」「支出」「貯蓄」
の3つの視点で行うのがポイントです。
①収入を把握する
まずは、家庭に入ってくるお金(手取り額)を正確に把握しましょう。
- 給与明細を見直す
- ボーナスの使い道を確認する
- 他の収入(副業、手当など)があるかをすべて洗い出す
②支出を洗い出す
次に、毎月の固定費と変動費を細かくチェックします。
できるなら、固定費と変動費を毎月or不定期の4分類で分けられるとよりわかりやすくなります。
| 固定費 | 変動費 | |
| 毎月 | 家賃・住宅ローン 水道光熱費 通信費 サブスク費 | 食費 日用品 医療費 交通費・ガソリン費 |
| 不定期 | 税金(固定資産税・自動車税など) 火災保険料 自動車保険料 車検費 | 旅行 家電・家具 冠婚葬祭 娯楽費 |
上記は一例ですが、この様に現在の支出について把握してみましょう。
③貯蓄と予備費を準備する
赤ちゃんにかかる費用は「突然」やってきます。
そのため、出産前に“使えるお金”を分けて準備しておくことが大切です。
- 出産準備資金(約20〜30万円)
- 緊急予備費(生活費3か月分)
- 教育資金の準備スタート(児童手当をそのまま貯金など)
赤ちゃん誕生前にパパがやっておきたいお金の準備リスト
ここからは、実際に何を準備すべきかをリスト形式で紹介します。
参考になれば幸いです。
①育児グッズの予算立て
- ベビーベッド:約10,000〜30,000円
- ベビーカー:約15,000〜50,000円
- チャイルドシート:約15,000〜40,000円
- おむつ・ミルクなど消耗品:月5,000〜10,000円
②出産にかかる医療費の備え
出産費用は、病院や分娩方法によって異なりますが、平均して約40万〜60万円が目安です。
【出産育児一時金(50万円)】があるため、自己負担を抑えることは可能ですが足りないことを想定して準備しておきましょう。
③保険の見直し(収入保障型は必要最小限でOK)
赤ちゃんが生まれる前は、将来の不安から保険を見直す家庭も多いと思います。
でも、なんとなく不安だからと必要以上に保険に入るのは、かえって家計を圧迫してしまうことも。
基本的に保険は「万が一のときに貯蓄でまかなえないもの」に絞るのが原則です。
たとえば、収入保障型の生命保険は、パパにもしものことがあったときに家族の生活を守るうえで有効です。
一方、出産や入院に備える医療保険については、高額療養費制度や一時金などの公的制度を活用すれば、多くは貯蓄で対応可能なケースもあります。
我が家の失敗談・成功談
実際に我が家が経験した失敗談・成功談についてです。
失敗談|あとから慌てた3つのこと
①育休中の手取りが想像より少なかった
妻の育休手当が支給されるのは産後しばらく経ってから。
しかも「手取りでこのくらいかな?」と思っていた額よりもだいぶ少なくて、生活費がギリギリに…。
産休・育休中は一時的に収入が減ることを想定して、事前に余裕をもった貯蓄を用意しておけばよかったと痛感しました。
②クレカの引き落としが残高不足で失敗
出産準備で一気に出費が増えた月、気づかずにクレジットカードの引き落としが残高不足に。
そのせいで期日に支払いができず、信用情報に傷がついてしまいました…
引き落とし口座の残高チェックはこまめにやっておくべきだったと後悔しました。
③ミルク代とおむつ代を甘く見ていた
「赤ちゃんって、こんなにおむつ使うの⁉」と驚いた日々。
さらに肌が弱かったためベビークリームや刺激の少ない石鹸などが必要になり、月ごとの出費が予想以上に増加。
事前に育児費用のモデルケースを知っておけば、家計の月予算にもっと現実味を持てたはずででした…
成功談|やっておいてよかった3つの工夫
①児童手当はすぐ専用口座に入金
児童手当(月15,000円)はそのまま貯金口座に移して、基本的に一切手を付けないルールに。
これが緊急時の備えになっていて、かなり心の余裕につながりました。
ちなみに、将来の教育資金は投資信託などで運用して準備しています!
②Amazon定期便&まとめ買いでおむつ代を節約
「おむつ」や「おしりふき」などはAmazonの定期便を利用して、5~15%割引+買い忘れ防止+ポイント還元という一石三鳥の方法でコスパ良く揃えられました。
店舗でセールが実施されているときはAmazonよりも安くなることもありますが、買いに行く時間やガソリン代などを考えると定期便の方がメリットがあると思い利用していました!
Amazon定期便は育児中の買い物の手間も減らせて、本当に助かりました!
③家計簿アプリで夫婦の情報共有がスムーズに
夫婦で「マネーフォワードME」を使い始めて、クレカや銀行口座の残高、何にどれぐらい使っているかなどの支出履歴が一目でわかるようになりました。
「今月ちょっと使いすぎてるね」などの会話が生まれ、自然とお金の価値観も共有できた気がします。
まとめ|パパの一歩が、家族の安心になる
家計の見直しは難しく感じるかもしれません。
ですが「赤ちゃんが来る」というワクワクと一緒に、産まれてくる赤ちゃんに対しての責任も生まれます。
家計管理は家族の未来を整える作業でもあります。
パパだからこそできるお金の準備。
今から始めれば、ママにも赤ちゃんにも安心をプレゼントできるようになります!